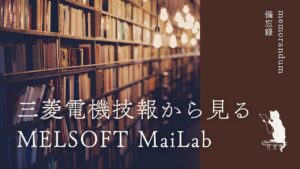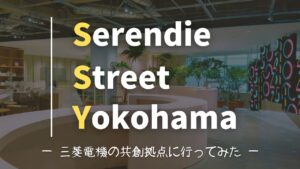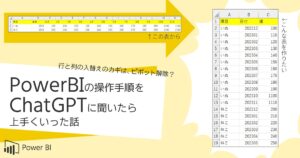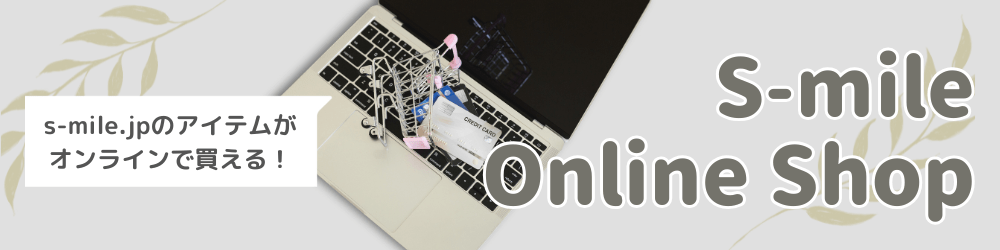【DXにモヤモヤしてきた方へ】中小企業の現場から考える「現実的なDXの始め方」
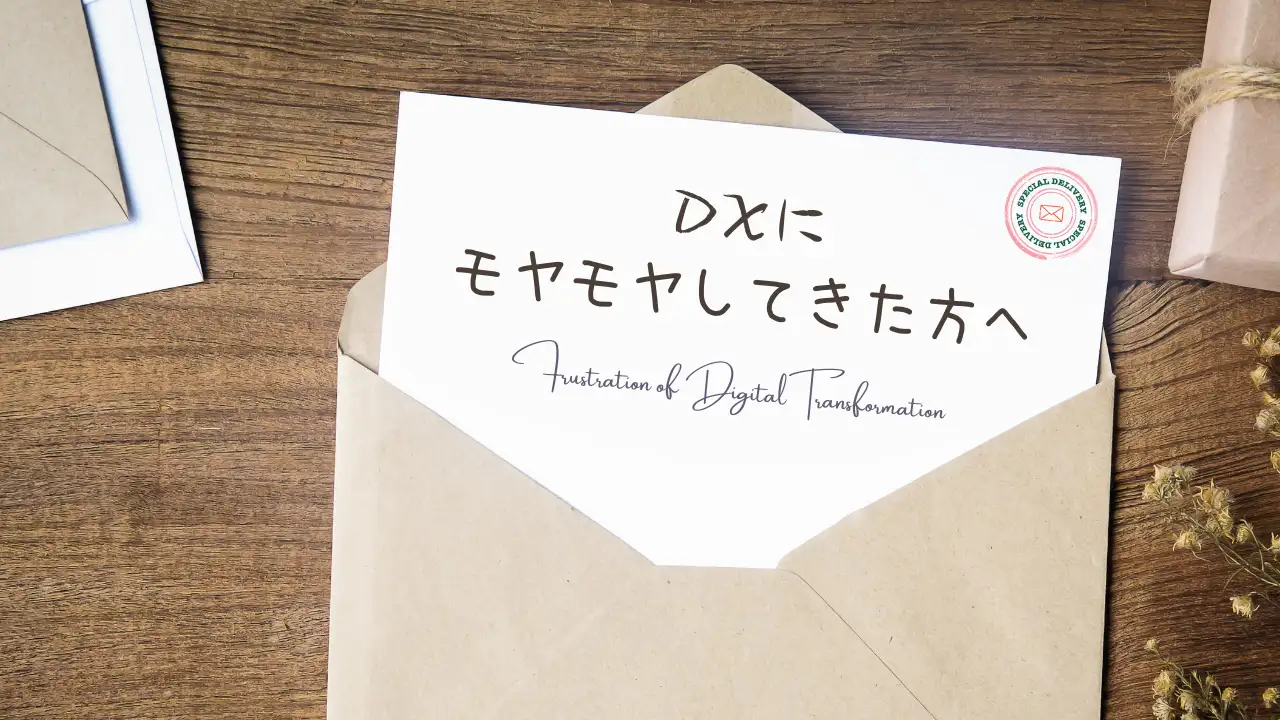
※本記事は、MEX2025で展示した内容をブログ用に加筆修正を加えた内容になります。
セミナーやニュースでDXの成功体験を耳にする機会が多くありますが、自社の現場を振り返ると「うちはなかなか…」と感じることはありませんか?本記事では、中小企業の現場で直面する課題に焦点を当て、無理なく始められるDXの始め方を探っていきます。
はじめに
DXの本来の意味
DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、総務省のウェブページでは以下のように定義されています。
デジタル・トランスフォーメーションは、デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していくような取組を指す概念である。
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd112210.html
単にシステムやツールを導入するだけではなく、それらをうまく活用することで、仕事の進め方や意思決定のスタイルそのものを見直し、より良い働き方を実現していくことが、本来のDXの目的になります。
現場での受け止め方
しかし現場からは「結局うちの会社ではどう進めればいいの?」「どこから始めれば良いの?」といった悩みをよく耳にします。
また、導入した後も「導入効果を実感できなかった」「現場に定着しなかった/結局使わなくなった」「ツールを覚えたり入力したり、手間だけ増えた」との声も同様に耳にします。
DXに取り組むときによくある課題・モヤモヤ
DXよりも前に取り組むべきこと
DXを会社全体の変革として一気に進めようとすると、会社全体を巻き込む必要があり、これには時間や費用がかさむので大きな負担となることがあります。
実は、DXよりも先に取り組むべき小さな変革というものがあります。
Digitization(デジタイゼーション)
既存の紙のプロセスをデジタル形式に変換すること。特定の業務や作業を効率化するためにデジタルツールを導入するイメージです。
例:対面の打ち合わせをWeb会議にする、紙で保存していた資料を電子データにする、等。
Digitalization(デジタライゼーション)
業務やプロセスそのものを自動化すること。
例:RPA(PC作業の自動化)、見積もりシステム(依頼からメール送付までを自動化)、IoT活用 等。
これらの小さな変革が、企業全体のDXへの土台となります。この土台は導入するシステムだけでなく、それを利用する人々の意識や働き方の変化も含まれます。
土台作りのモヤモヤ
- モヤモヤ① 手間が増える
もちろん、新しいツールを導入すると、これまでの業務に少なからず影響が出ます。便利さを実感するまでには、操作に慣れる時間が必要になることもあります。 - モヤモヤ② コストがかかる
規模の大きなシステムを一度に導入しようとすると、それなりの時間やコストがかかります。もし期待した効果が十分に得られなければ「DXは難しい」と感じてしまうこともあります。
これらのモヤモヤを最小限にするためにも、まずは小さな取り組みから始め、少しずつ成果を積み重ねていくことが大切です。
DX推進で企業が直面する課題と現場視点の解決法
多くの企業では、次のような課題に直面することがあります。
- どこからDXを始めればよいのか分からない
- 導入したシステムが活用されず効果を感じられない
- 自社に合わなかったケースがある
1つずつ見ていきましょう。
1. どこからDXを始めればよいのか分からない
日常業務の中で「考えなくてもできる作業」や「ルーチンワーク」になっている部分は、デジタルツールで効率化できる可能性があります。また紙や口頭でのやり取りが多かったり、属人化業務が多かったりする場合も、改善のチャンスになります。
2. 導入したシステムが活用されず効果を感じられない
新しいツールや仕組みは、最初はどうしても慣れが必要で手間に感じることもあります。
そのため、なるべく既存の業務に自然に馴染むように組み込むことが重要です。
しかしながら、しばらく運用しても負担感が強い場合は、導入したシステムが現場の規模やニーズに合っていない可能性も考えられます。
例えばSFA(営業支援システム)は営業活動を共有できる便利な仕組みですが、いきなり大規模なシステムは定着が難しいこともあります。まずは、
- 日報をPCで作成する文化
- 日報を活用したマネジメント
という文化を定着させることから始めると良いかもしれません。その後、
- 定型的な入力にして、入力の手間を減らしたい
- 効率的に情報を活用したい
といったニーズに応じて、SFA等のシステムやツールを導入するとスムーズだと思います。
3. 自社に合わなかったケースがある
急な大規模システム導入は「合わない」と感じやすい
大規模な構想を一度に実現しようとすると、コストをかけたぶん期待と現実のギャップで「合わない」と感じやすいです。そのためまずは「FAXの利用を減らす」「紙のカタログを電子化する」といった、身近な改善から取り組むのがおすすめです。
コンサルや商社に相談するのも選択肢の一つ
ツールやシステムは非常に多く存在します。自社に合うシステムを探す時間が限られている場合は、外部(コンサルや商社)に相談するのも選択肢の一つです。ただし、その際は予算や目的を明確に伝えることが大切です。あいまいに進めてしまうと、コストや機能が必要以上に膨らむリスクがあります。
しかし「外部に任せっきり」にならないように
そして何より大切なのは、外部に任せきりにしないことです。現場で実際に使う自分たちが主体となり、小さな取り組みを繰り返しながら改善を重ねていくことが重要です。近年では、従来のPDCAよりも「Checkから始める」改善サイクルも注目されています。まず現状を把握し、小さな試行を重ね、結果を踏まえて次のプランを立てていくようなアプローチを行うと、無理なくDXを推進できるかと思います。
終わりに
ルーティンワークやめんどくさい定期的な作業、誰でもできる作業は、どんどんデジタルの力を借りてラクをしていきましょう。